連結会計担当者が不足する今、企業がとるべき3つの対応策とは?
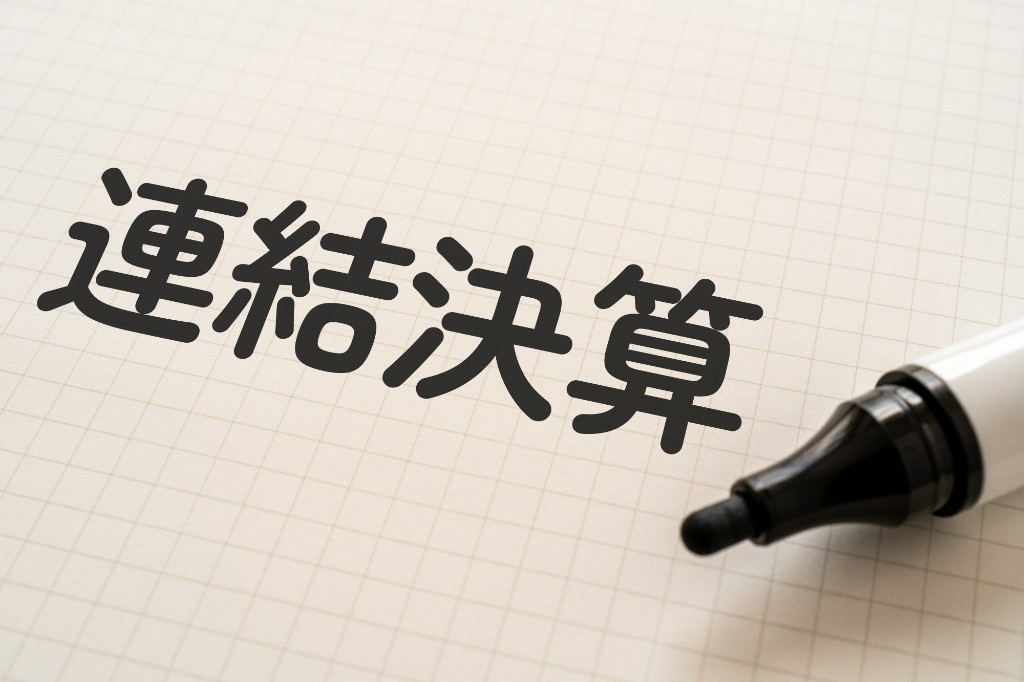
企業経営において「決算早期化」や「財務の透明性強化」が求められる中で、連結会計の重要性はかつてないほど高まっています。
しかし、連結決算を担う専門人材は市場でも希少であり、多くの企業が「経験者が見つからない」「ノウハウが属人化している」「人手が足りず業務が回らない」といった課題を抱えています。
特に、複数の子会社を持つ中堅~大企業にとって、連結決算の正確性・スピードは株主や金融機関からの信頼にも直結します。
本記事では、こうした背景の中、今後企業がどのような視点で会計部門を改革すべきかを「未来展望型」で提案します。
今、経理部門に起こっている変化とは
連結会計の複雑化と専門性の高まり
かつては月次決算や単体決算のみで足りた時代もありましたが、グローバル化・M&A・IFRS(国際財務報告基準)導入の流れを受け、連結会計が当たり前の時代となりました。
その結果、経理業務は「高度化」と「複雑化」が進み、対応できる人材も限られてきています。
経理人材の採用難と属人化の弊害
経理部門は他部門と比べて人材流動性が低い傾向にあり、特に中小企業では「〇〇さんがいないと連結決算が組めない」といった属人化が深刻化しています。
この属人化は、退職・休職による業務断絶リスクを常に内包しています。
さらに、会計人材の採用市場では、連結決算や会計システムに精通した人材は人気が高く、年収も上昇傾向にあるため、中堅企業には獲得が困難です。
決算早期化プレッシャーの高まり
企業のIR強化や経営判断の迅速化の流れにより、決算開示の「早期化」「正確性の確保」が重視されています。
上場企業では、決算短信提出の短縮や内部統制監査対応が求められ、連結会計のプレッシャーは高まる一方です。
企業の将来を見据えた3つの改革ポイント
人材戦略の再構築(リモート・副業・多様化)
これからの人材戦略は「従来型の正社員採用」にこだわらない柔軟性が必要です。
リモートワークの定着:地方在住でも優秀な人材を確保できる。
副業・業務委託の活用:即戦力のプロフェッショナル人材を部分的に活用。
定年後再雇用の仕組み:会計経験者の知見を継承する制度設計。
さらに、経理部門を「デジタル・リスキリング」の対象とし、既存社員に連結会計や会計システムの知識を身に着けさせる育成戦略も並行して進めることが重要です。
業務の標準化と社内教育の強化
属人化を解消し、どの担当者でも一定水準の業務が行える仕組みを整えることは喫緊の課題です。
業務マニュアルの整備:連結精算表作成や子会社からのデータ収集手順を文書化。
業務棚卸と業務プロセスの可視化:重複や無駄を洗い出し、効率化の余地を特定。
研修制度の拡充:会計基準の理解、会計システム操作に関するeラーニング導入など。
標準化は新任者でも短期間で業務をキャッチアップできる体制を作る上で不可欠です。
テクノロジー導入による業務効率の最大化
人材不足を補い、かつ業務スピードと正確性を高めるためには、テクノロジーの導入が避けて通れません。
クラウド連結会計システム:子会社とのデータ連携や、各種帳票の自動生成が可能。
RPAによる仕訳やチェック業務の自動化:単純作業の人的ミスを防止。
AIによる異常値検知や経営分析の自動化:経営層の判断材料をリアルタイムで提示。
たとえば、従来5日かかっていた連結精算表の作成が、クラウドシステム導入により1.5日に短縮されたという事例もあり、業務効率化とコスト削減の両立が期待できます。
10年先を見据えた連結会計部門の理想像
リモート・自動化された会計体制
将来的には、経理業務の大部分が「リモート+自動化」で完結する体制が主流となるでしょう。
これは、オフィス勤務が難しい優秀人材の活用や、パンデミックや災害時の業務継続にも対応するBCP施策ともなります。
AI活用による予測型財務管理の実現
AIを活用することで、単なる過去データの集計だけでなく、「未来予測」や「経営シナリオのシミュレーション」が可能になります。
これにより、経営者はより戦略的な判断が可能となり、財務部門は経営参謀としての役割を強めていくでしょう。
人的リスクの最小化とBCP対応
退職・病気・育休などでキーパーソンが抜けても、業務が停止しない体制づくりは不可欠です。
クラウドやマニュアル、AIツールを活用し、「誰がいなくなっても業務が回る」仕組みを整えることが、未来の経理部門に求められる姿です。
連結会計業務改革に向けて今できること
現状業務の棚卸と課題の可視化
まずは、現状の業務フローと担当範囲を「見える化」し、どこにボトルネックや属人化があるのかを明確にしましょう。これは改革の第一歩です。
小さく始めるクラウドシステム導入
いきなり全社導入ではなく、まずは連結精算表作成やレポート作成からシステムを使ってみるなど、「スモールスタート」での導入が成功の鍵です。
外部パートナー活用による人的負担の軽減
連結決算の一部業務をBPO(業務アウトソーシング)や外部の専門家に委託することで、内部リソースをコア業務に集中させることができます。
連結会計改革は「未来への投資」
連結会計の人材不足は、一過性の課題ではなく、今後の企業経営に継続して影響を与えるテーマです。
企業が今とるべきは「場当たり的な人員補充」ではなく、「中長期的に持続可能な体制づくり」です。
柔軟な人材戦略、業務の標準化と教育、そしてテクノロジーの活用。
この3つの視点を軸にした改革が、今後の企業の競争力を大きく左右するでしょう。


