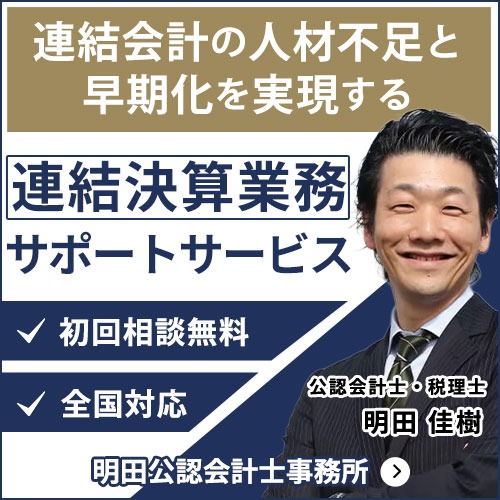2025.06.17
連結決算の限界と効率化の第一歩
連結決算の限界と効率化の第一歩:属人化からの脱却を目指して
企業グループが成長するにつれ、連結決算業務の複雑さは加速度的に増していきます。「月次や四半期決算のたびに各社からExcelでデータを集め、科目の統一や内部取引の消去に膨大な時間を取られている」「担当者が限られており、誰かが欠けると進まない」——こうした悩みを抱えている企業は少なくありません。実際、連結決算は高度な専門性と正確性が求められる業務であり、限られたリソースで対応し続けるには限界があります。
属人化によるリスクと業務のひずみ
多くの企業では、連結決算が特定の担当者に依存している「属人化」の状態にあります。これは短期的には業務のスピード感を保てる一方で、担当者の退職や異動が発生すると、そのノウハウがごっそり抜け落ちるリスクを抱えています。また、人的ミスの発見や修正に多くの時間を費やす構造になりやすく、結果として本来の財務分析や経営へのフィードバックが後回しになってしまいます。
Excelの限界と非効率の構造
Excelは柔軟で手軽に扱えるツールではありますが、連結決算のように大量のデータを扱い、複雑なルールが絡む処理には限界があります。リンク切れや数式の不整合、バージョン管理の混乱は日常茶飯事。チェック作業や修正依頼にかかる時間が増え、結果として「作業のための作業」が増殖していくのです。
業務効率化のカギは「標準化」と「自動化」
では、どうすればこの負のサイクルから脱却できるのでしょうか。鍵となるのは、業務の標準化と、可能な部分の自動化です。たとえば、各子会社からのデータ収集をフォーマット化し、統一されたルールでの提出を徹底するだけでも整合性チェックの手間は大きく軽減されます。また、連結仕訳や内部取引消去のルールをシステム化することで、人的ミスのリスクも減らせます。
近年では、クラウド型の連結会計システムやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用し、定型作業を自動化する企業も増えています。これにより、担当者は「処理する人」から「確認し、分析する人」へと役割をシフトできるようになります。
自社に合った改善方法を見つける
もちろん、すべてを一気に変える必要はありません。まずは現状の業務フローを可視化し、どこにボトルネックがあるのかを明確にすることが第一歩です。その上で、自動化すべき業務と、専門性を活かして人が判断すべき業務を切り分けていきましょう。
外部の専門家に相談するのも一つの手です。第三者の視点から業務を見直すことで、思わぬ改善ポイントが見えてくることもあります。
まとめ
連結決算業務に限界を感じているというのは、決して自社だけの問題ではありません。むしろ、それは次の成長段階へのサインとも言えます。手作業に頼る時代から、標準化と自動化によって効率化を図る時代へ。属人化から脱却し、より戦略的な経理財務へとシフトするための一歩を踏み出してみませんか?
企業グループが成長するにつれ、連結決算業務の複雑さは加速度的に増していきます。「月次や四半期決算のたびに各社からExcelでデータを集め、科目の統一や内部取引の消去に膨大な時間を取られている」「担当者が限られており、誰かが欠けると進まない」——こうした悩みを抱えている企業は少なくありません。実際、連結決算は高度な専門性と正確性が求められる業務であり、限られたリソースで対応し続けるには限界があります。
属人化によるリスクと業務のひずみ
多くの企業では、連結決算が特定の担当者に依存している「属人化」の状態にあります。これは短期的には業務のスピード感を保てる一方で、担当者の退職や異動が発生すると、そのノウハウがごっそり抜け落ちるリスクを抱えています。また、人的ミスの発見や修正に多くの時間を費やす構造になりやすく、結果として本来の財務分析や経営へのフィードバックが後回しになってしまいます。
Excelの限界と非効率の構造
Excelは柔軟で手軽に扱えるツールではありますが、連結決算のように大量のデータを扱い、複雑なルールが絡む処理には限界があります。リンク切れや数式の不整合、バージョン管理の混乱は日常茶飯事。チェック作業や修正依頼にかかる時間が増え、結果として「作業のための作業」が増殖していくのです。
業務効率化のカギは「標準化」と「自動化」
では、どうすればこの負のサイクルから脱却できるのでしょうか。鍵となるのは、業務の標準化と、可能な部分の自動化です。たとえば、各子会社からのデータ収集をフォーマット化し、統一されたルールでの提出を徹底するだけでも整合性チェックの手間は大きく軽減されます。また、連結仕訳や内部取引消去のルールをシステム化することで、人的ミスのリスクも減らせます。
近年では、クラウド型の連結会計システムやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用し、定型作業を自動化する企業も増えています。これにより、担当者は「処理する人」から「確認し、分析する人」へと役割をシフトできるようになります。
自社に合った改善方法を見つける
もちろん、すべてを一気に変える必要はありません。まずは現状の業務フローを可視化し、どこにボトルネックがあるのかを明確にすることが第一歩です。その上で、自動化すべき業務と、専門性を活かして人が判断すべき業務を切り分けていきましょう。
外部の専門家に相談するのも一つの手です。第三者の視点から業務を見直すことで、思わぬ改善ポイントが見えてくることもあります。
まとめ
連結決算業務に限界を感じているというのは、決して自社だけの問題ではありません。むしろ、それは次の成長段階へのサインとも言えます。手作業に頼る時代から、標準化と自動化によって効率化を図る時代へ。属人化から脱却し、より戦略的な経理財務へとシフトするための一歩を踏み出してみませんか?